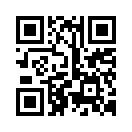2013年07月18日
埋立承認申請意見書>チーム・ザン
これからポストに投函です。
平成25年7月18日
沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿
提出者:北限のジュゴン調査チーム・ザン 鈴木雅子他一同
連絡先:〒905-0011 沖縄県名護市宮里4-12-8
電話: 携帯電話:0980-43-7027
Eメール: n-hokugen.19@kjd.biglobe.ne.jp
・利害関係内容
私たちは、沖縄島周辺に生き残った国の天然記念物で絶滅に瀕したジュゴンの生息
環境を保全するために活動している「北限のジュゴン調査チーム・ザン」のメンバー
です。本件事業の該当海域におけるジュゴンの活発な採餌活動を記録し、この地域個
体群の保護、繁殖、および沖縄県全体の個体群の維持を図る立場から、ここに意見を
述べます。
・意見
本件公有水面埋立承認申請は、先に提出された環境影響評価補正評価書に基づき手
続きが進められていますが、その補正評価書ではジュゴンの個体群維持に及ぼす影響
が過少評価されており、このまま事業が進められた場合、復元が不可能な重大な過ち
を犯す可能性があることを危惧し、わが国唯一のジュゴンの生息地を有する沖縄県知
事として「沖縄のジュゴン」の地域個体群の保全策が認められない以上は、今埋立申
請は承認すべきではありません。
理由
・PVA評価の過ち
事業者は、ジュゴンの個体群存続可能性分析(PVA)を行い、その結果環境収容力が
低下した場合の絶滅リスクは、事業が実施されない場合と有意な差が認められないと
し、代替施設の設置に伴う海草藻場の消失がジュゴンの個体群維持に及ぼす影響は小
さいと結論づけました。しかし、この分析は大きな過ちを犯しています。
日本のジュゴン個体数は非常に少なく、正に絶滅に瀕しています。このような状況
の中で私たちに出来ることとはいったい何でしょう。ジュゴンもトキと同じように人
工繁殖させ、野生に導入すれば良いのでしょうか(系統群の問題はありますが)。
ジュゴンの飼育の歴史は、1955年にサンフランシスコの水族館がパラオ産の個体を飼
育したのに始まり、これまでに世界で30例以上の飼育記録がありますが、残念ながら
飼育下で繁殖に成功した事例がひとつもありません。一方、野生下ではアセスの調査
で親子のジュゴンが確認されたように、繁殖を続けています。つまり、ジュゴンの保
存(存続)に必要なのは、ジュゴンが安全に暮らせる環境と十分な餌場を確保するこ
とであり、私たちに出来ることも、唯一生息地を保全することだけなのです。
また、沖縄のジュゴンは世界のジュゴン分布の東の北限にあたり、この地域個体群
を保存することは、世界のジュゴンにとって遺伝的多様性確保の観点からも大変重要
です。それぞれの地域個体群は、棲息地の地元が保全に乗り出さなければ守れないこ
とを考えれば、沖縄県の責任は一層重大です。
・海砂の採取の及ぼすジュゴンの餌場への影響
ジュゴンの唯一の餌である海草は、海岸近くの海底の砂に藻場を形成することから、
海砂採取による海草藻場への悪影響を懸念しています。 今回の埋立用の海砂採取予
定地が、ジュゴンの回遊ルートに重なることも大きな懸念材料です。ジュゴンはとて
も敏感な生き物で、人間活動との接触を嫌います。広大で良好な藻場があり、それま
でよく利用していた辺野古海域を、2004年のボーリング調査を巡る海上での騒動
以来、忌避している(アセス調査も含め防衛局による作業強行がジュゴンを追い出し
たとも言えます)例があり、海砂の採取や運搬に伴う騒音や海域の攪乱がジュゴンの
生活や生態を乱し、さらなる生息環境の悪化につながる恐れがあります。
・埋立用、購入土砂の問題
購入土砂も大問題です。アセス逃れのために政府は購入土砂を使用するとしていま
すが、多くの地域で海砂をはじめ土砂採取による環境への悪影響が大きな問題になっ
ています。地域住民の反発も強く、埋立申請添付書類の中で採取場所の特定がされて
いないことにも示されるように、容易に確保できるとは思われません。
仮に確保できたとしても、有害物質が含まれていないかどうかはもちろん、特に沖
縄の亜熱帯島嶼生態系にとって、まったく生態系の違う場所から持ち込まれる土砂に
含まれる移入種の問題、生態系の攪乱は危機的です。それは、世界自然遺産登録をめ
ざす政府(環境省)の方針にも反するものです。
また、購入土砂について、福島原発事故による放射能汚染の懸念も拭えません。採
取場所がどのような場所で、どのような生態系を持ち、土砂に何が含まれているか、
採取場所以外の土砂が混入していないか、等をどのように調査・点検し、移入種や有
害物質の混入を避けることができるのか、その方法をきちんと示さない限り、島外か
らの土砂持ち込みを行ってはならないと考えます。
・海面の消失について
1−ジュゴンの生息域の減少
事業実施区域周辺において生息する個体A は嘉陽沖にほぼ常在しており、事業実施区
域においては確認されていないとし、個体Cは平成20 年度より嘉陽沖や大浦湾で確認
されるようになったが、行動範囲は大浦湾東側海域までの範囲にあり、施設等の存在
による海面消失に伴いジュゴンの生息域が減少することはほとんどないと記されてい
ますが、野生動物の生活パターンとしては余りに「想定範囲」が乏しいと思われま
す。成体の繁殖期や若い個体の行動、台風等の自然環境変異におけるジュゴンの行動
への考察も想定もありません。北部沿岸に常駐している個体が台風時には浅いリーフ
に近寄れず、辺野古海域を経て金武湾まで回遊して採餌しているという知見も聞きま
す。希少なジュゴンの個体群維持において保存すべき生息環境の範囲は、生存幅の安
全性を最優先すべきです。
2− 餌場の減少
事業実施区域周辺において確認される個体AとCについての餌場の利用への考察が
「予定範囲」に野生動物を閉じ込めるような発想自体が余りに稚拙であり「科学性」
を疑わせます。特に個体C については行動範囲が広く、大浦湾内の海草藻場も利用し
ていると認識し、施設等の存在に伴う海草藻場の減少はジュゴンの餌場の減少につな
がる可能性が考えられるとしながら、その環境保全措置はあいまいであり「その影響
をできる限り低減するために、海草藻場の生育範囲を拡大する環境保全措置を講ず
る。」としていますが具体的に科学的に保障された記述がありません。海草の生育範
囲
を拡大する環境保全措置は、ジュゴンが好み、採餌した場所はどのような理由があろ
うと手を付けず「保全」し、環境悪化の負荷を減らすことです。
加えて「過去には辺野古地先の海草藻場において食跡が確認されている」と記しなが
ら、「事業実施区域周辺で確認される現在のジュゴンの行動範囲や餌場の利用状況か
らみて、辺野古地先の海草藻場へ移動し採食する可能性は小さい」というような結論
は余りに杜撰であり、「辺野古地先の海草藻場は都合により使わせない」としか読め
な
い記述です。野生のジュゴンを人間の管理化でコントロールしようと言う姿勢は不遜
極まります。
・流れ、波浪、水質の変化
「施設等の存在に伴う波浪、流れ、水質の変化は、代替施設の周辺でみられるが、
ジュゴンが餌場として利用している嘉陽地先の海草藻場の分布範囲においては変化が
生じないものと予測され、ジュゴンの生息環境に影響を及ぼすことはほとんどない
と考えられる。」とありますが、沖縄のジュゴンがわずかな個体数で生き残ってきた
歴史と行動をみれば、嘉陽の小さな海草藻場だけに依存して生き延び、繁殖してきた
とは誰も考えません。個体Cの行動を見ても餌場を求め遠く西海岸から東海岸まで来
遊し、これからも沖縄島南北の餌場を利用する可能性は十分にあります。埋立事業に
よって、かつて金武湾までの回遊ルートの中核である辺野古海域の環境が改変され
ルートが南北に断ち切られれば、沖縄のジュゴンの個体群への影響は計り知れないで
しょう。
・海洋構造物の出現
「個体C は行動範囲が広く、事業実施区域周辺においては天仁屋崎周辺か大浦湾東側
海域に至る範囲で確認され、大浦湾内の海草藻場で確認された食跡も個体C による可
能性が考えられ、個体C は大浦湾の東側海域を主に移動経路として利用している可能
性が考えられ、大浦湾西側海域の海草藻場で個体C によるとみられる食跡が確認され
ている」とし、埋立地及び進入灯、燃料桟橋の設置が個体C の行動範囲に変化を与え
る可能性を認めながら、「保全措置」には触れず「事後調査を行い、調査結果をもと
に必要な措置を講じる」というのでは全くの『手遅れ』でしかありません。施設の出
現により個体Cの行動が変化してしまってから、いったいどのような「措置」が講じ
られ、それで個体C他の周辺地域に生息するジュゴンたちの「保全」に寄与できるの
でしょうか?甚だ疑問です。
・水中音の評価基準
「ジュゴンの生息状況調査におけるヘリコプターによる追跡調査では、飛行高度を
150m まで低下して行動の観察を行ったが、ジュゴンの行動に変化を与えないことを
確認した。」では何らジュゴンへの保全対策にはなりません。余りに安易です。
施設併用時においては、たまにとぶヘリコプターのレベルでないことは、離発着する
米軍機の多様な機種を考えれば、ジュゴンのみならず水面下の生態系への影響は計り
知れません。
・水の濁り
「工事中の濁りは汚濁防止膜の開口部から拡散するが、ジュゴンの生息が頻繁に確認
されている嘉陽地先の海域には濁りはほとんど拡散しないものと予測され、工事中の
濁りがジュゴンの生息環境や餌場とする海草藻場の生育環境に影響を与えることはほ
とんどないと考えられる。」とありますが、幾度も言及しますが、野生の生物の行動
範囲や採食活動を人間の都合で「管理」はできません。水の濁りによる餌場の放棄や
海草藻場の劣化の責任を追うのは事業者であり、野生生物ではありません。
ジュゴンが嘉陽に定住して欲しいのは事業者の勝手な都合でしかなく、この事業の
環境保全措置としてお粗末過ぎる結論であり、科学性のカケラもありません。
・その他の要因
海草藻場の分布域の変化や台風の来襲やそれに伴う高波浪が、ジュゴンの浅海部の餌
場への来遊を阻害する要因について、昨今の自然環境の変化への考察がまったくない
のは不自然です。
人為的影響として、米軍演習及び海上作業の状況をみると、2003年度までは宜野
座沖〜金武湾において海上工事が継続して実施されていたが、2004年 以降特に
増加した傾向はみられないとしていますが、2004年以後に新基地建設に向けての
アセス調査等の作業によって辺野古海域へのジュゴンの来遊が疎外されていることは
周知の事実です。
また、辺野古海域の餌場の利用についても個体Aは嘉陽に定住し、個体Bは
古宇利島に定住し、個体Cについても辺野古地区(大浦湾西部)や大浦湾奥部の海草
藻場で確認され行動範囲が広いとしながら、嘉陽地区の海草藻場を主に利用して
辺野古地区前面の海草藻場を利用する可能性は小さいと推測し、その他のジュゴン
の辺野古海域への来遊の可能性も切り捨ててしまっています。
全てが事業者に都合の良い「想定内」に収めようとしていますが、ジュゴンは飼育動
物ではなく、あくまで野生の営みの中で採食し、繁殖しているという現実を無視して
います。
・嘉陽地区における防災護岸の影響
最後に現存するジュゴンの生息海域において、現在進行中の防災護岸建設についても
今後のジュゴンの餌場の環境変化を想定しなければならないと考えています。
この地域は、土地改良など陸上の改変の少ない背後地の水循環環境がほとんど人工的
な工作物のない砂浜とリーフの構成する沿岸において海草藻場の豊かな海洋生態系が
保持されている北部沿岸でも稀有な環境です。それ故に、ジュゴンやウミガメにとっ
て安定した餌場や繁殖の場として保障されて来ました。しかし、昨今の地球的規模の
環境変異がもたらす異常な台風襲来等により、古来からジュゴンと共に暮らして来た
地域住民の浸水被害や漂砂による被害が度重なり、地元住民の安全のためには新たな
対策が求められ、陸上部分への護岸の設置が開始されています。私たちはジュゴン保
護の側面から、地元住民や沖縄県土木行政、名護市への環境保全策と住民の暮らしの
安全の両立を求めて働きかけて来ました。環境工学から生物の専門家まで様々な研究
者の知見によれば、この特異な環境は、背後地の環境から海域の海流や気流の条件な
ど様々な要因に依拠し、陸上の工作物(護岸)建設がただちに影響が出ることは少な
いが、特に強い潮の流れによる砂の移動は予想でき、それによる海域の環境変化の可
能性を示唆されています。私たち保護団体と該当事業者による護岸建設後の環境モニ
タリングははずせない状況です。
さて、本件公有水面埋立承認申請は、先に提出された環境影響評価補正評価書に基
づき手続きが進められていますが、この埋立周辺域に生息する個体AとCの2頭の生息
域がほとんど嘉陽と限定されています。現在は台風後も比較的に安定した餌場として
活用されていますが、この小さな面積の海草藻場が今後も安定的である保障はどこに
もありません。万一、嘉陽の環境が変化し、ジュゴンの餌場が失われた場合、この
地域個体群は個体群維持のために移動し、より安定的な餌場を求めるのは必須です。
現在も旺盛な食欲を見せる個体群が将来の繁殖を維持するためにも、嘉陽の10倍の
面積を持つ辺野古海域の海草藻場を保全すべきであるのは自明です。
以上の理由から、ジュゴン個体群存続に致命的な悪影響を与える辺野古埋立承認申
請は、断じて認めてはなりません。
Posted by 北限のジュゴン調査チーム・ザン at 00:53│Comments(0)