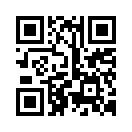2010年08月23日
学習会「海岸線と島の未来」
 夕方には名護市内に戻り、「沖縄の砂浜が危ない!…変わりゆく海岸線と島
夕方には名護市内に戻り、「沖縄の砂浜が危ない!…変わりゆく海岸線と島の未来」というテーマの緊急学習会を開催した。
十分な周知もできなかったが、中南部からもたくさんの参加者が駆けつけ
関心の高さと問題の深刻さを実感した。
講演1−砂の生産とサンゴ礁の生物侵食…石垣島白保の研究から
鈴木倫太郎(駒澤大学応用地理研究所)
講演2−サンゴ礁の島と砂の話
長谷川均(国士舘大学教授)
現場報告−沖縄の海岸線の変貌
田代豊(名桜大学国際学群)他
質疑/会場を含めた意見交換
まず、この問題に向かうには私たち自身が沖縄の砂浜やサンゴ礁の島や砂
についての知見が必要であり、加えて、現状確認が必須であると考えての
学習会と巡検であった。
鈴木さんからは本土と違った「生物起源」の集積物としてのサンゴ礁の砂
浜と「生物侵食」や人間活動の与える影響についてのお話があった。
長谷川さんからは世界の海岸線の紹介も含めて砂浜海岸と岩石海岸、サンゴ
礁海岸と分類される中「日本のサンゴ礁は浜から始まる」と、日本のサンゴ
礁の特性を指摘。日本の砂浜海岸と災害は「人が住んでいるゆえの」地盤沈
下や高波から人々の暮らしを守るために護岸が造られること。日本の海岸の
特性ゆえの必要悪と土建産業の社会構造の指摘がされた。
また、砂でできた島である洲島の例として、チービシの神山島の砂の汲み
上げによる島の形の変化、久米島のはての浜の台風による海浜の変化と
自然の護岸としてのビーチロックの存在を紹介された。
また、泡瀬・辺野古・大浦湾の海浜についてはその自然の多様性の豊かさ
は奇跡的であり、湿地の持つ浄化作用のもたらしたものでないかと指摘さ
れた。
最後に、日中の巡検を踏まえて田代さんから浚渫や人工ビーチの影響で海
岸侵食が激しくなり、2007年から養浜事業が盛んになったこと、加えて
その発想の貧困さが今の無残な現状になっていることの指摘がされた。
会場からは沖縄の海浜は「浜と磯と潟」と表現できるとの指摘や、今帰仁
はかつては砂丘があったがそれが陸域からどんどん搬出されて今はなくな
ったという事実が報告されるなど、興味深い話が聴くことができた。
また、なぜ海浜を守るための策がハードであるのか?建設のための建設で
しかないという現状への怒りと、その構造を変えるために私たちに何がで
きるか?との声があがった。
今回はまず、「この頃沖縄の海辺がおかしい・・・」と感じている私たち
自身がその現場を確認し、今何が起きているのかを知るために沖縄の海浜
の特長や成り立ちについての見聞を深めるという第一歩の試みだった。
問題の深刻さや重さは予想以上であり、即解決の道筋は見えないけれども、
今回の試みを第一歩として、様々な事例を集め、知見を集め、また人間の
都合だけでない様々な視点を私たち自身が持ち、常に海浜を見守り、機会
を創って触れ合い、情報を交換し、そこから見える課題を発信することが
必要ではないだろうか?
多数の発言を頂いた参加されたみなさんにはまだまだ時間も足りなく、
もっと論議を深めたい場でしたが、この一歩を踏まえた問題の共有から始
まるのだと考えます。「何だか近頃、海辺がおかしい・・・と思っていたら
・・・、あっちもこっちもとんでもないことになっていた!」ことは全員
が驚愕する事態になっていたのですから・・・もう、ほっとけない・・でし
ょう!!!
Posted by 北限のジュゴン調査チーム・ザン at 12:27│Comments(0)